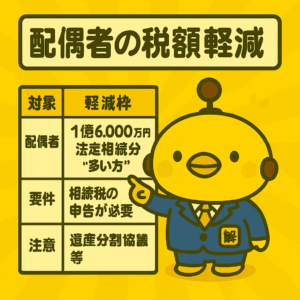小規模宅地等の特例とは?|相続税を大きく減らせる土地評価の優遇制度【2025年最新】


小規模宅地等の特例とは?|相続税を大きく減らせる土地評価の優遇制度【2025年最新】
80%減額・330㎡上限・家なき子特例・計算方法を完全理解!
🏠📊 小規模宅地等の特例を完全マスター
相続税を大幅に減額できる小規模宅地等の特例を正しく理解しよう!
区分・減額率・要件・限度面積まで完全網羅します!
小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)とは、
被相続人が居住用または事業用に使用していた宅地等を、一定の要件を満たす相続人が相続する場合、相続税の課税対象となる土地の評価額を大幅に減額できる制度です。
最大80%の減額が可能で、相続税の負担を大きく軽減できることから、相続対策の中でも特に重要な制度とされています。
💡 特例の効果
最大80%の土地評価額減額
居住用330㎡・事業用400㎡・貸付用200㎡まで
🔍 用途区分による特例の内容
📅 組み合わせ限度面積
• 特定居住用宅地等(330㎡)+特定事業用宅地等(400㎡)
• 最大合計:730㎡まで
貸付事業用宅地等が含まれる場合
• 貸付用の限度面積(200㎡)は別途按分計算
• 居住用・事業用との調整計算が必要
🔍 面積の組み合わせには上限あり
📊 特例適用後の評価額を計算しよう
🔍 小規模宅地等の特例適用の流れ
1️⃣ 土地の用途要件
• 被相続人の居住用宅地
• 被相続人の事業用宅地
• 被相続人の貸付事業用宅地
• 同族会社の事業用宅地
注意点
• 相続開始直前の使用状況
• 農地・採草放牧地等は対象外
• 貸付業は区分が異なる
🏠 用途による区分が重要
2️⃣ 相続人要件
• 被相続人の配偶者
• 同居親族
• 事業承継者
• 家なき子(別居親族)
家なき子の要件
• 相続開始前3年間持家なし
• 配偶者・親族の持家に住んでいない
• 特別な関係にある法人の持家に住んでいない
👨👩👧👦 相続人により要件が異なる
3️⃣ 継続要件
• 相続税申告期限まで所有
• 途中での売却・贈与不可
• 持分の一部売却も不可
使用継続要件
• 居住用:申告期限まで居住
• 事業用:申告期限まで事業継続
• 貸付用:申告期限まで貸付継続
📅 申告期限(10か月)まで継続
4️⃣ 申告要件
• 相続税申告書への明細書添付
• 申告期限内の提出
• 特例により税額がゼロでも申告必要
必要書類
• 小規模宅地等についての明細書
• 続柄を証明する書類
• 住民票・戸籍謄本等
📄 申告漏れは特例適用不可
💰 具体的な計算例で理解しよう
🧮 計算の考え方
実際面積と限度面積の小さい方が適用対象
例:実際250㎡ vs 限度330㎡ → 250㎡が適用対象
2. 減額の計算
適用対象面積 × 1㎡当たり評価額 × 減額率
例:250㎡ × 20万円/㎡ × 80% = 4,000万円減額
3. 特例後評価額
通常評価額 - 減額分 = 特例後評価額
例:5,000万円 - 4,000万円 = 1,000万円
💡 限度面積と減額率がポイント
問題1:特定居住用宅地等の限度面積と減額率
特定居住用宅地等について、限度面積と減額率の組み合わせはどれでしょうか?
問題2:貸付事業用宅地等の減額率
貸付事業用宅地等(アパート経営等)の減額率はどれでしょうか?
問題3:家なき子特例の適用要件
別居していた親族(家なき子)が特定居住用宅地等の特例を適用する場合の要件はどれでしょうか?
🚨 家なき子特例の要件厳格化
• 過去の持家有無の確認強化
• 配偶者・親族の持家居住歴チェック
• 特別関係法人の持家も対象
注意すべきケース
• 一時的な賃貸居住
• 法人名義の住宅
• 親族名義の住宅居住
📋 事前の要件確認が必須
⏰ 継続要件違反のリスク
• 申告期限前の売却
• 居住中止・事業中止
• 用途変更
違反時の処理
• 特例の遡及的取消し
• 追徴課税・延滞税
• 修正申告の必要性
⚖️ 10か月間の継続が重要
📄 申告漏れのリスク
• 特例により税額がゼロでも申告必要
• 明細書の添付が必須
• 期限内申告が原則
申告漏れの影響
• 特例の適用不可
• 通常評価額での課税
• 期限後申告でも救済なし
📅 申告期限の厳守が必要
🏢 同族会社との関係
• 被相続人が役員等である法人
• 相続人が事業を継続
• 持株要件の充足
注意点
• 法人の事業内容
• 貸付業の除外
• 相続人の役員就任
🏢 法人形態での事業承継時の要件
Q. 複数の宅地がある場合はどうすればよいですか?
A. 有利な組み合わせを選択できます。
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を合わせて最大730㎡まで適用可能です。貸付事業用宅地等が含まれる場合は別途調整計算が必要になります。
Q. 二世帯住宅の場合は特例を適用できますか?
A. 構造により適用可否が変わります。
区分所有登記がされていない二世帯住宅であれば、被相続人と相続人がそれぞれの居住部分について特例を適用できる可能性があります。詳細は税理士にご相談ください。
Q. 老人ホームに入居している場合は適用できますか?
A. 一定の要件を満たせば適用可能です。
介護が必要で老人ホームに入居している場合、元の自宅が空き家状態でも、一定の要件を満たせば特定居住用宅地等の特例を適用できる場合があります。
Q. 店舗兼住宅の場合はどう計算しますか?
A. 用途ごとに按分して計算します。
居住用部分は特定居住用宅地等、事業用部分は特定事業用宅地等として、それぞれの面積に応じて特例を適用します。双方とも80%減額が適用されます。

💬 カイピヨくんのひとこと
自宅やお店を相続するなら、この特例は"逃したらもったいないピヨ!"でも、要件がちょっと厳しいから、事前に"使えるかどうかチェック"をするのがコツピヨ〜✨
💪 小規模宅地等の特例を正しく理解して相続税負担を軽減
小規模宅地等の特例は相続税を大幅に軽減できる重要な制度です。
適用要件や継続要件を正しく理解し、
計画的な相続対策で税負担の軽減を図りましょう!