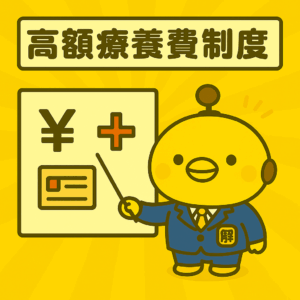被扶養者とは?知っておきたい保険料ゼロの条件と注意点


被扶養者とは?知っておきたい保険料ゼロの条件と注意点
家族の生活設計に大きく関わる重要な制度
Contents
📌 被扶養者(ひふようしゃ)とは?
被扶養者とは、健康保険に加入している本人(=被保険者)に扶養されている家族で、一定の条件を満たすことで保険料を払わずに保険に加入できる人のことです。
💡 重要なポイント
健康保険証は発行されますが、保険料はゼロ円!
配偶者・子ども・親など、家族の生活設計に大きく関わるポイントです
配偶者・子ども・親など、家族の生活設計に大きく関わるポイントです
🧑👩👧👦 誰が被扶養者になれる?
原則として、被保険者に生計を維持されている家族が対象です。
📝 重要な条件
一般的には「3親等以内の親族」で、かつ生計維持関係がある場合に認められます。
💰 被扶養者になるための収入条件は?
被扶養者は「一定の収入以下」である必要があります。主な基準は以下の通りです。
🚨 重要な注意点
社会保険上の「扶養」は、税制上の扶養(所得税控除)とは条件が異なります。
✅ 扶養から外れるとどうなる?
💡 重要なポイント
扶養の認定・喪失は申請ベースなので、収入増加があったら必ず申告を!
🏥 被扶養者の健康保険証の活用
被扶養者になれば、被保険者と同じように医療給付を受けられます(自己負担3割)。以下の制度も対象です:
📄 被扶養者認定の手続き
📝 手続きのポイント
認定は会社の健康保険組合または協会けんぽが行います。
🎓 FP3級での出題ポイント
✅ よくある勘違いQ&A
Q. 配偶者のパート収入が月10万円なら扶養OK?
→ ✅ 年収130万円未満かつ週20時間未満であれば原則OK!
Q. 被扶養者は保険料を支払う?
→ ❌ 扶養内であれば本人負担はなし(事業主が負担)
Q. 妻が扶養内で出産すると、一時金は出る?
→ ✅ 出産育児一時金は健康保険から支給されます!

🐥 カイピヨくんのひとこと
「保険料ゼロでも安心の医療保障ピヨ!でも"年収130万の壁"には注意ピヨ!」
🚀 もっと詳しく学ぼう
被扶養者制度を理解したら、次は実際の家計プランに活かしてみましょう!
夫婦の働き方と収入バランスを最適化することで、家計の負担を大きく軽減できます。