保険料とは?社会保険・民間保険の支払いの仕組みをわかりやすく解説【FP3級対応】


保険料とは?社会保険・民間保険の支払いの仕組みをわかりやすく解説【FP3級対応】
保険料の種類・計算方法・控除制度の基礎知識
Contents
💰 そもそも保険料とは?
保険料とは、保険契約に基づき「将来のリスクに備えるために定期的に支払うお金」のこと。
保険の種類(社会保険/民間保険)によって、計算方法や負担者、控除制度が異なります。
🎯 保険料の役割
多くの人が少しずつお金を出し合い、万一の時に必要な人に給付を行う「相互扶助」の仕組みを支える大切な資金です。
📊 保険料の種類と分類
🏛️ 社会保険と民間保険の保険料
📈 【図解】保険料の基本構造(例:社会保険)
💼 労使折半の仕組み
【給与から差し引かれる保険料の構造】
💰 給与(報酬月額)
├─ 🏢 会社負担分
└─ 👤 個人負担分
↓
合わせて保険料として納付
※厚生年金・健康保険などは「労使折半」
🏢
会社負担分
企業が支払う部分
👤
個人負担分
給与から天引き
⚖️
労使折半
50%ずつ分担
🔍 民間保険の保険料の決まり方(生命保険・医療保険など)
📋 保険料に影響する要素
💸 保険料控除(所得控除)で税金が安くなる!
📄 確定申告や年末調整で以下の控除が可能です
💡 節税効果の計算例
年間12万円の保険料控除を受けた場合(所得税率10%の場合)
節税額:12万円 × 10% = 1.2万円
🎓 FP3級でよく出るポイント
📚 重要な出題テーマ
❓ よくある質問(Q&A)
Q:会社員だけど、保険料って全部給与から天引きされてる?
A:はい、社会保険料は会社がまとめて納付しています。給与明細に記載されている分が自己負担分です。
Q:フリーランスの保険料は?
A:国民健康保険・国民年金に加入し、自分で保険料を納めます。
Q:保険料が高くて困っている…
A:収入が減少したときは、国民年金・健康保険には減免制度があります。
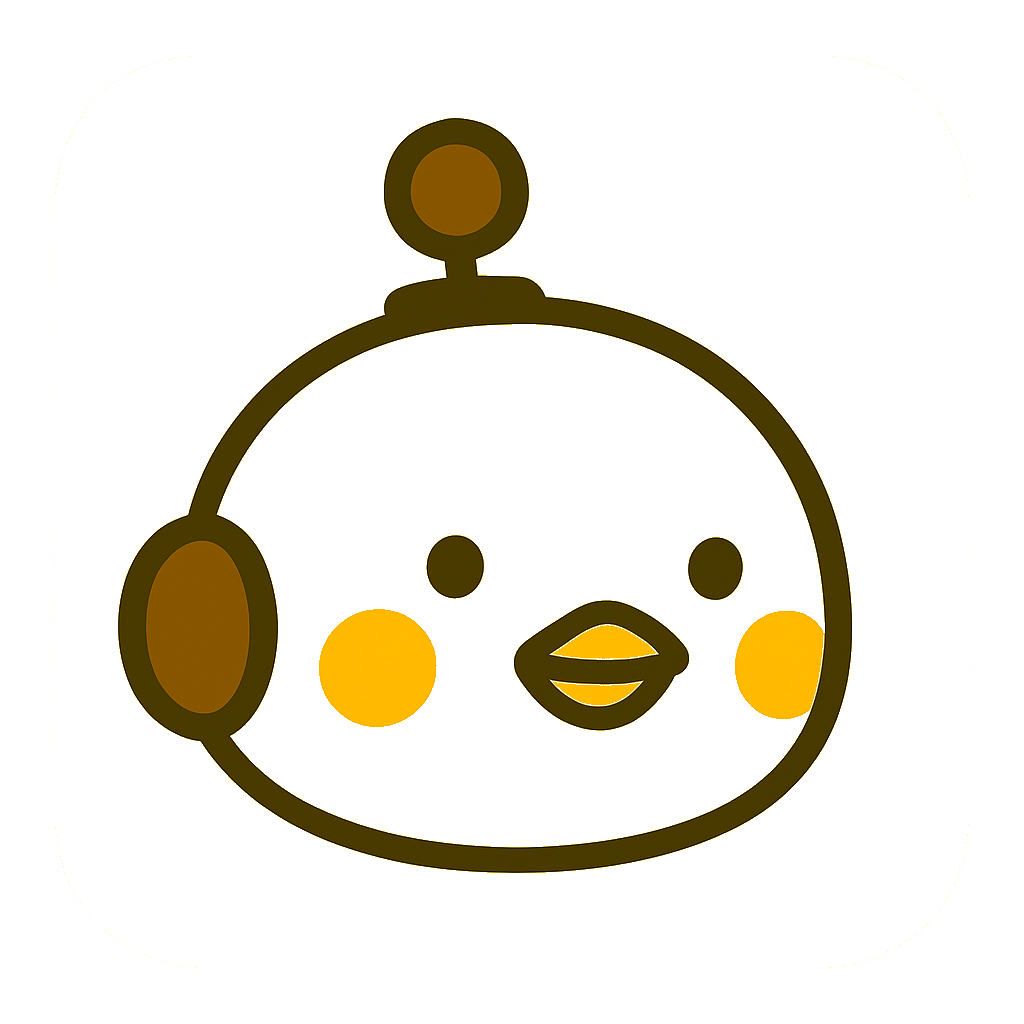
🐥 カイピヨくんのひとこと
「"毎月払ってる保険料"、ただの出費じゃないピヨ!税金を減らす味方にもなるピヨよ!」
🔗 公的リンク・参考サイト
✅ まとめ
💰 保険料は将来への投資と節税の両方を実現
保険料は単なる支出ではなく、将来のリスクに備える投資であり、同時に税金を減らす効果もあります。
社会保険と民間保険の仕組みを理解し、適切な保険料の管理で安心できる将来設計を行いましょう。


