配偶者の税額軽減とは?|相続税が0円になることもある特例【FP3級対策】
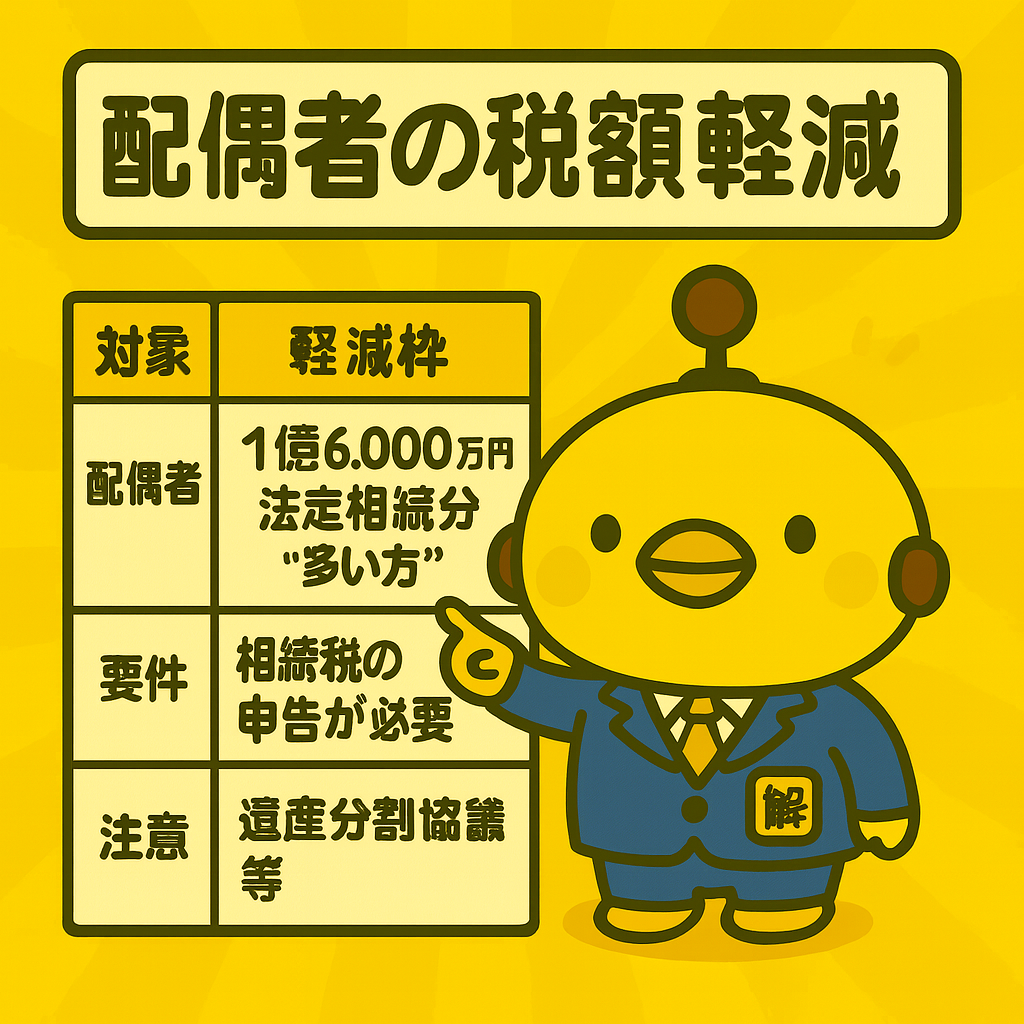
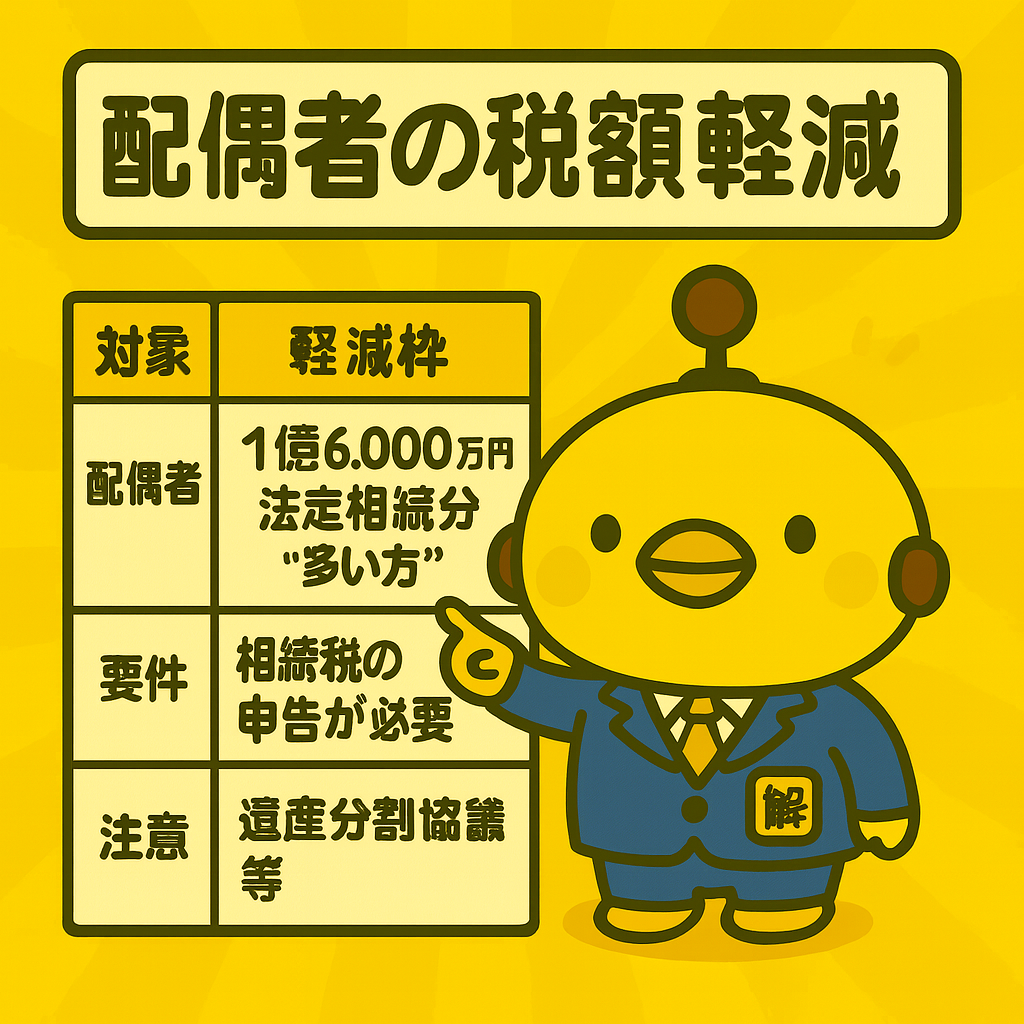
配偶者の税額軽減とは?|相続税が0円になることもある特例【FP3級対策】
配偶者が相続する場合の強力な税額軽減措置
Contents
📌 配偶者の税額軽減とは?
配偶者の税額軽減とは、相続税の計算において、
配偶者が取得した財産に対して、
最大で相続税がかからなくなる特例です。
具体的には、次の金額までは配偶者に相続税がかかりません
①
1億6,000万円まで
絶対的な非課税枠
②
法定相続分まで
配偶者の法定相続分
💡 重要ポイント
どちらか「大きい方」まで非課税になるので、
配偶者の相続税は0円になるケースも多いのが特徴です。
配偶者の相続税は0円になるケースも多いのが特徴です。
✅ 適用条件
💍
正式な婚姻関係
戸籍上の配偶者のみ
内縁関係は対象外
内縁関係は対象外
🎁
財産取得要件
相続・遺贈で取得
実際に財産を受け取る必要
実際に財産を受け取る必要
📄
申告義務
税額0円でも申告必要
10か月以内に提出
10か月以内に提出
⚠️ 申告を忘れると軽減は受けられません!
相続税額が0円になる場合でも、
必ず相続税の申告書を提出する必要があります
必ず相続税の申告書を提出する必要があります
✅ 具体例で理解!
🧮 配偶者が2億円を相続した場合
🎯 設定:
・夫が死亡し、妻が2億円の財産を相続
・相続人は妻のみ(法定相続分:100%)
・夫が死亡し、妻が2億円の財産を相続
・相続人は妻のみ(法定相続分:100%)
📊 比較:
① 1億6,000万円(絶対的非課税枠)
② 2億円(法定相続分100%)
→ 2億円の方が大きい
① 1億6,000万円(絶対的非課税枠)
② 2億円(法定相続分100%)
→ 2億円の方が大きい
✅ 結果:
→ 2億円まで非課税
→ 相続税額:0円
→ 2億円まで非課税
→ 相続税額:0円
📝 別パターン:子がいる場合
・相続人:妻・子1人
・妻の法定相続分:1/2(1億円)
・妻が実際に取得:2億円
① 絶対的非課税枠
1億6,000万円
② 法定相続分
1億円
結果:1億6,000万円まで非課税
残りの4,000万円に課税
残りの4,000万円に課税
🆚 税額軽減と基礎控除の違い
👥
基礎控除
相続人全体に適用される
遺産から差し引く控除
遺産から差し引く控除
💍
配偶者の税額軽減
配偶者個人に対して適用される
優遇措置
優遇措置
📊 適用の順序
① まず基礎控除で課税遺産総額を計算
② 各相続人の相続税額を算出
③ 配偶者には税額軽減を適用
② 各相続人の相続税額を算出
③ 配偶者には税額軽減を適用
📘 FP3級試験ポイント
💰
基本ルール
「1億6,000万円 or 法定相続分のどちらか大きい方まで非課税」
と暗記すること!
と暗記すること!
🆚
違いの理解
控除と税額軽減の違いに注意
適用対象・段階が異なる
適用対象・段階が異なる
📄
申告要件
配偶者の
「相続税申告は不要になることがある」
という記述が正誤問題で出やすい
「相続税申告は不要になることがある」
という記述が正誤問題で出やすい
🧮
計算問題
法定相続分との比較
どちらが大きいかの判定
実際の軽減額の計算
どちらが大きいかの判定
実際の軽減額の計算
⚠️ 頻出の間違いパターン
「配偶者は相続税の申告が不要」← これは間違い!
税額が0円でも申告書の提出は必要です
税額が0円でも申告書の提出は必要です
📝 試験対策のコツ
配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」「法定相続分」「申告必要」がポイント!
基礎控除との違いもセットで覚えましょう。
💡 実務上の注意点
⏰
申告期限の厳守
相続開始から
10か月以内に申告
遅れると軽減なし
10か月以内に申告
遅れると軽減なし
👥
二次相続への影響
配偶者が多く相続すると
次の相続で課税
長期的視点が重要
次の相続で課税
長期的視点が重要
📋 その他の注意点
- 内縁関係は対象外 - 戸籍上の夫婦関係が必要
- 遺産分割協議が必要 - 財産取得が確定してから適用
- 将来の相続税対策 - 一次・二次相続の総合検討が必要

🐤 カイピヨくんのひとこと
「配偶者がたくさんもらっても、相続税がかからないって…びっくりピヨ!
でも申告は忘れずに出さないとダメだから注意ピヨ~!」
🔗 参考リンク・出典
✅ まとめ
💍 配偶者の税額軽減を理解して相続税対策に活用しよう
配偶者の税額軽減は非常に強力な制度です。
ただし申告義務を忘れずに、将来の二次相続も含めた総合的な検討が重要です!


