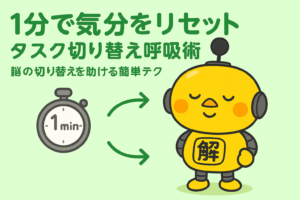うつ病で退職」は労災になる? 医師の診断書から申請までの進め方と注意点

⚕️ うつ病での退職と労災認定:知っておくべき基礎知識
長時間労働やパワハラなどで心が追い込まれ、ついに「うつ病で退職」――。
その時、「ただの自己都合退職」として片付けられてしまうと、補償や支援制度を受けられなくなる可能性があります。
しかし、条件を満たせば「業務上の精神障害」として労災認定が認められ、給付や慰謝料を請求できるケースもあります。
本記事では、うつ病を理由とする退職が労災と認定されうる要件、医師の診断書の役割、申請・進め方、よくあるトラブルと対応策を解説します。
⚠️ 最初にお読みください:重要な注意事項
1. まずは専門家への相談を
この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別のケースについては、必ず弁護士・社会保険労務士・医師などの専門家にご相談ください。
2. 早期受診が最優先
心身の不調を感じたら、まず精神科・心療内科を受診してください。健康を取り戻すことが何よりも大切です。
3. 自己判断は避けてください
労災認定の可否は個別の事情により大きく異なります。この記事だけで判断せず、専門家の助言を受けてください。
🏥 労災とは?精神疾患(うつ病)が対象になるケース
📚 厚生労働省公式情報:労災(労働者災害補償保険)は、業務中や仕事が原因で発症・悪化した傷病に対して補償を行う制度です。従来は怪我や肉体的疾病が中心でしたが、近年は精神障害(うつ病・適応障害など)による労災認定も増えています。
労災(労働者災害補償保険)は、業務中や仕事が原因で発症・悪化した傷病に対して補償を行う制度です。
従来「怪我や肉体的疾病」のケースが中心だったが、近年は精神障害(うつ病・適応障害など)による労災認定も増えています。
📊 最新データ:令和3年度の厚生労働省データによると、精神障害による労災請求件数・支給決定件数ともに年々増加傾向にあります。ただし、認定率は約31〜32%程度と、認定のハードルは高い状況です。
ただし、精神疾患すべてが認められるわけではなく、所定の要件を満たす必要があります。
📋 うつ病で労災として認められるための3要件
📚 厚生労働省公式基準:労災(精神障害)認定には、主に以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。また、2023年9月に認定基準が改正され、カスタマーハラスメント(顧客や取引先からの著しい迷惑行為)や感染症リスクの高い業務なども評価対象に追加されました。
出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」、 マネーフォワード「うつ病の労災認定は難しい?」
| 要件 | 内容・ポイント |
|---|---|
| ① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること |
うつ病(気分障害等)が認定対象の疾病に含まれている。医師の診断が必要。 対象:ICD-10第V章「精神および行動の障害」のうち、認知症(F0)やアルコール・薬物依存(F1)を除くもの うつ病:「F3 気分(感情)障害」に分類され、労災対象 |
| ② 発病前おおむね6か月以内に業務による強い心理的負荷があったこと |
長時間労働、パワハラ、過重業務、重大なトラウマ的出来事などが該当。 評価方法:「業務による心理的負荷評価表」に基づき「強」「中」「弱」の3段階で評価し、「強」と判断される場合に要件を満たす 例:月100時間程度の時間外労働、上司からの人格否定、パワハラなど |
| ③ 業務以外の心理的負荷や個人要因のみで発病したとは認められないこと |
私生活ストレス(離婚、家族の死亡など)・既往歴などを排除できる程度で因果関係を示す必要。 注意:私生活の出来事があっても、主な原因が業務上のストレスであれば労災認定の可能性あり |
⚠️ 2023年9月の改正ポイント
新たに追加された具体的出来事:
・カスタマーハラスメント(顧客や取引先からの著しい迷惑行為)
・感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した
これにより、より幅広いケースで労災認定される可能性が高まりました。
特に業務起因性を示すため、過重な労働時間の記録、上司の言動・配置変更・パワハラ記録、メール・業務指示文書など、客観的証拠が重要になります。
⏱️ 退職後も労災申請できる?時効・留意点
📚 重要情報:労災の申請は退職後でも可能です。退職・転職していても、労働基準監督署へ請求できます。ただし、給付の種類によって時効(消滅時効)があるため注意が必要です。
・療養補償給付・休業補償給付:給付対象となる日から2年で時効消滅
・障害補償給付・遺族補償給付:5年のものもある
※時間が経つほど因果関係を立証する証拠収集が難しくなるリスクが高まります
退職後1年経過しても認定された事例も報じられています。ただし、早めの申請が望ましいです。
📝 診断書の取り方・使い方 — 進め方ガイド
⚠️ 最優先:まず受診してください
労災申請を考える前に、まず精神科・心療内科を受診し、適切な治療を受けることが何よりも大切です。健康を取り戻すことが最優先です。
申請の流れ(7ステップ)
精神科・心療内科で診断を受け、「うつ病」等の診断名をきちんと出してもらう。
退職検討段階でも早めに受診を。継続的な診察を受けることが極めて重要。
労災請求用の診断書を作成してもらう。
病名・発症時期・症状・業務との関係性の記述を求める(医師に協力を仰ぐ)。
業務日報・タイムカード・メール記録・業務命令文書・配置異動記録・上司とのやりとりなどを保管。
パワハラ・プレッシャーの記録も重要。
労災請求書・診断書・証拠資料を揃えて、勤務していた事業所を管轄する労働基準監督署に提出。
労基署が事業主に事情聴取、資料確認、必要なら労働局・監督署調査を行う。
時間を要するケースが多い(6か月〜1年程度)ことも。
認定されたら、療養補償給付(医療費)、休業補償給付(休業中の賃金補填)等が支給される。
認定に納得できなければ不服申し立て(審査請求など)を行う。
申請段階で傷病手当金を受給していた場合、労災認定後は返還請求がなされるケースがある。
(すでに支給された傷病手当金・医療給付分を調整する)
💼 退職する際に注意すべき制度・他の給付制度との関係
| 制度 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 傷病手当金 |
健康保険適用対象で、退職前に一定要件を満たしていれば受給可能。 ただし、労災認定された場合には返還・調整されることがある |
| 失業保険(基本手当) | うつ病や業務起因性で退職した場合、会社都合退職/特定理由離職者として扱われる可能性があり、受給期間・優遇措置がある |
| 損害賠償請求 |
労災認定があれば、会社に対して安全配慮義務違反を根拠に慰謝料請求を併せて行うケースもある ※労災保険からは慰謝料は支給されないため、別途請求が必要 |
| 退職交渉 | 退職届・退職手続き時に、うつ病・業務負荷を理由に会社へ説明を残しておくと証拠性が高まる |
⚠️ よくあるトラブル・リスクと対策
| トラブル | 原因・リスク | 対策 |
|---|---|---|
| 診断書に業務因果が書かれない | 医師に因果性を記述してもらえない | 医師に事情説明し、業務との関連性を伝える。必要に応じて別の医師のセカンドオピニオンも検討 |
| 証拠が不十分・矛盾がある | 日報・メール等記録がなかった | 記憶だけでなく文書証拠・証人を確保。弁護士に相談 |
| 認定されずに請求却下 | 要件を満たしていない、因果不明 | 不服申し立て・専門家へ相談。審査請求の手続きを検討 |
| 療養給付後、傷病手当金返還請求 | 二重受給状態と判断される | 申請段階で制度の切替や返還リスクを確認 |
| 時効にかかる | 遅れて申請した | 早めに請求。療養・休業給付は日ごとに2年消滅時効 |

"うつで退職=会社のせい"とは即断できないピヨけど…条件が揃えば労災になる可能性もあるピヨ!
でもね、一番大事なのはまず健康を取り戻すことピヨ。受診・証拠保全は早めにやるピヨ〜。
そして必ず専門家(弁護士・社労士・医師)に相談するピヨ。一人で抱え込まないでピヨ🐥💙
📌 まとめ:まず動くべきチェックポイント
✅ 1. 早期受診・診断書取得
うつ病と診断されたら、業務との関連性を医師に説明したうえで診断書を取得。
※最優先は治療です。健康を取り戻すことが何よりも大切
✅ 2. 業務記録・証拠の保全
勤務時間・残業、上司指示、会議資料・メールなどを保管。
客観的証拠が労災認定の鍵となります。
✅ 3. 労災請求の準備
請求書類の準備、労基署提出、調査対応態勢を取る。
※退職後でも申請可能ですが、時効に注意
✅ 4. 並行制度の検討
傷病手当金・失業保険・損害賠償などを併用・検討。
それぞれの制度の関係性を理解しておきましょう。
✅ 5. 専門家相談(最重要)
労働問題に精通した弁護士・社会保険労務士に早めに相談。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別のケースについては必ず専門家にご相談ください。
💙 一人で抱え込まないでください
うつ病など精神疾患は、適切な治療とサポートで回復が可能です。
まずは医師の診察を受け、必要に応じて弁護士・社労士などの専門家に相談してください。
あなたの健康と権利を守るために、専門家のサポートを受けることをお勧めします。