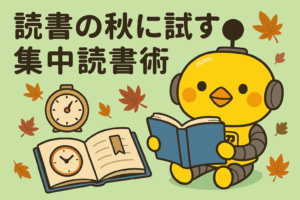退職後の“給付金サポート”って本当に必要?自分でできる手続きと注意点まとめ
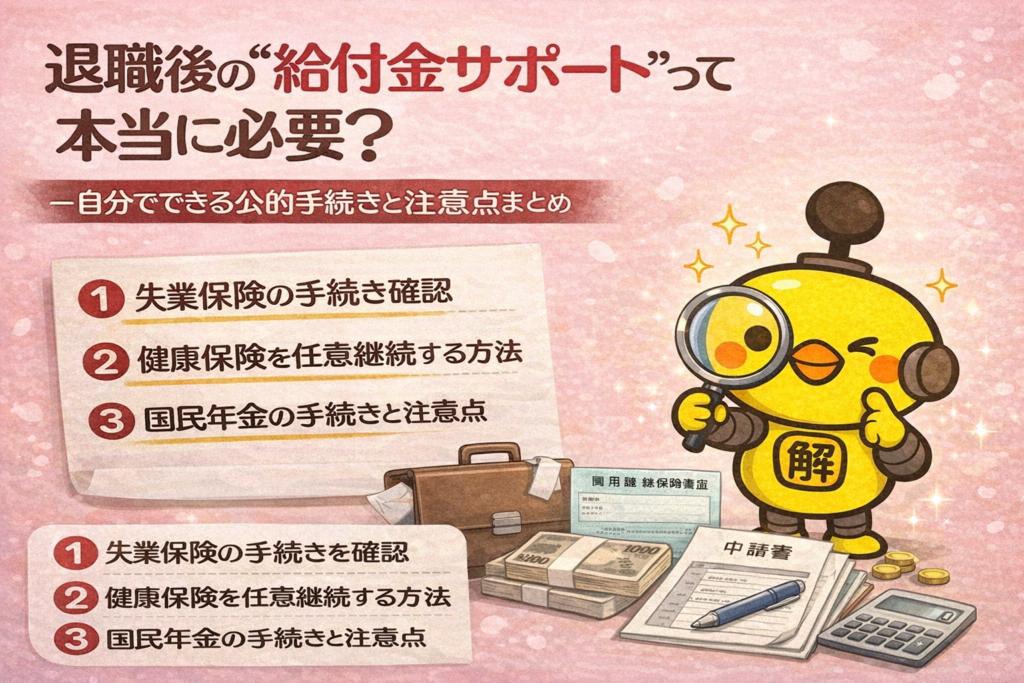
通勤中やスキマ時間に、音声で退職後の給付金制度について学習できます
※音声と記事の内容は同じです。お好みの方法で学習してください
💰 「給付金サポート」って何なの?—"最大数百万円もらえます"系の注意点と、自分でできる公式ルート—
退職を検討している時、SNSやネット広告で「退職後に最大数百万円の給付金がもらえる!」「知らなきゃ損する給付金制度」といった情報を目にしたことはありませんか?
これらの「給付金サポート」「社会保障給付金サポート」といったサービスは、既に国が用意している公的制度を使った申請のお手伝いをするもので、給付金そのものが新しいものではありません。
多くの手続きは自分で無料でできます。この記事では、具体的にどんな制度があり、どこで相談すべきか、そして給付金サポートを利用する際の注意点を、できる限りわかりやすく解説します。
🔍 「給付金サポート」の実態—業者が案内するのは既存の公的制度—
SNS等でよく見かける「退職後に最大◯◯万円の給付金がもらえる」というフレーズ。
この"給付金"の正体は、国や自治体が既に用意している公的制度です。具体的には以下のようなものが含まれます。
💡 給付金サポートが案内する主な公的制度
- 雇用保険の基本手当(失業保険):失業中の生活を支援
- 再就職手当:早期に再就職した場合に支給
- 教育訓練給付:スキルアップのための受講費用を補助
- 傷病手当金(健康保険):病気やケガで働けない期間の所得補填
- 求職者支援制度:雇用保険を受給できない人への月10万円の給付+職業訓練
- 国民年金保険料の免除・猶予:失業時の保険料負担軽減
- 住民税の減免:自治体によって異なる
📚 エビデンス:これらは全て公的制度です。詳細は各公式サイトで確認できます。
これらの制度は元々無料で申請できるものです。
給付金サポート業者は、これらの制度を案内し、申請手続きをサポートする代わりに、給付金の15〜30%程度(数十万円)の手数料を請求するのが一般的です。
💰 給付金サポートの料金相場—実際いくら取られる?—
給付金サポートを利用した場合の一般的な料金体系は以下の通りです。
💸 サポート料金の相場
成功報酬型(最も一般的):
給付金総額の15〜30%が相場。例えば給付金総額が100万円なら、15〜30万円がサポート料として差し引かれます。
固定料金型:
給付金額に関わらず、15〜30万円の定額料金を請求するケース。
初期費用+成功報酬型:
初期費用として数万円を先払いし、さらに給付金の一定割合を成功報酬として支払う形式。
⚠️ 注意:サイトによっては料金体系が不明確なケースもあります。契約前に必ず具体的な金額を確認してください。
🚨 高額なサポート料を払う前に知っておくべきこと
多くの公的制度は自分で無料で申請できます。
ハローワーク・協会けんぽ・自治体の窓口では、無料で丁寧に案内してもらえます。
高額なサポート料(15〜30万円)を払う前に、まず公的窓口で無料相談することを強くお勧めします。
📋 「自分でできる」公的制度の申請方法—無料で使える窓口まとめ—
それぞれの制度について、具体的にどこで相談・申請すればいいのかを整理しました。
1. 雇用保険(失業給付・再就職手当・教育訓練給付など)
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワークインターネットサービスで最寄りの窓口を検索できます。
• 離職票(退職後に会社から郵送されます)
• 雇用保険被保険者証
• マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書
• 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
• 印鑑
• 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
STEP1:離職後、ハローワークで求職申込みを行う
STEP2:受給資格の決定(7日間の待機期間あり)
STEP3:雇用保険説明会への参加(指定日に実施)
STEP4:4週間に1回、失業認定を受ける(求職活動の報告が必要)
STEP5:失業認定日の約1週間後に給付金が振り込まれる
📚 エビデンス:基本手当の受給には「離職日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること」が原則です。自己都合退職の場合、給付制限期間(2ヶ月または3ヶ月)がありますが、会社都合退職や特定理由離職者の場合は給付制限がありません。
2. 傷病手当金(健康保険)
協会けんぽ、または加入している健康保険組合
会社員の場合、多くの方が「協会けんぽ」に加入しています。
全国健康保険協会(協会けんぽ)公式サイト
傷病手当金は退職後も継続して受給できる場合がありますが、条件があります:
• 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があること
• 退職日に出勤していないこと
• 退職時に既に傷病手当金を受給中、または受給できる状態であること
退職前から医師の診断と勤務先での手続きが必要なので、早めに確認しましょう。
📚 エビデンス:傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない期間、標準報酬日額の3分の2相当額が最長1年6ヶ月支給される制度です。退職後の継続給付には厳格な要件があります。
3. その他の公的制度
市区町村の国民年金窓口、または日本年金機構
失業した場合、前年所得に関わらず免除を受けられる特例があります。
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
お住まいの市区町村役場(税務課)
失業や収入の激減により、住民税の減免を受けられる場合があります。
自治体によって要件が異なるため、必ず確認してください。
例:東京都港区、練馬区
消費者ホットライン(188):状況整理や疑問点の相談に有効
どの制度を利用すべきか迷った場合、まず公的窓口や消費者ホットラインで相談することをお勧めします。
📚 エビデンス:厚生労働省・ハローワークの公式サイトには、各制度の詳細な要件・手続き方法が掲載されています。まずは公式情報を確認することが重要です。
出典: ハローワークインターネットサービス、 厚生労働省、 協会けんぽ
💡 簡易失業給付金シミュレーション
給付金サポート業者が提示する「最大◯◯万円もらえる」という金額が妥当かどうか、自分で確認してみませんか?
このツールでは、失業保険・傷病手当金・教育訓練給付・控除免除などを含めた総額を概算し、サポート料(15〜30万円)を払う価値があるかを判断できます。
退職前の給与情報を入力するだけで、あなたがもらえる給付金の概算総額がわかります。
※令和7年度(2025年度)の最新制度に基づく概算です
📊 給付金シミュレーションを試す✅ 給付金サポートを使う前に確認すべきチェックリスト
高額なサポート料を払う前に、以下のポイントを必ず確認してください。
⚠️ 契約前の必須チェック項目
□ 具体的な制度名(傷病手当金、失業給付等)を明示しているか?
「給付金」「サポート金」などの曖昧な表現だけでなく、具体的な公的制度名を説明しているか確認。
□ サポート料の金額と計算方法が明確か?
「給付金の◯%」という表示だけでなく、具体的な金額の上限が明示されているか。給付金が不支給の場合の返金条件も確認。
□ 運営者情報が明記されている?
会社名・代表者名・住所・電話番号が明確に記載されているか(特定商取引法の表示義務)。
□ まず公的窓口(ハローワーク・健康保険)で無料相談したか?
自分が受給資格があるか、必要書類は何かをまず無料で確認してから、サポート利用を検討すべき。
□ 「必ずもらえる」「100%受給」などの断定表現がないか?
給付金の支給は条件を満たす必要があり、断定的な表現は誇大広告の可能性。
□ 自分で申請する方法を調べたか?
多くの手続きは自分で無料でできます。高額なサポート料を払う前に、まず自力で挑戦してみましょう。
📚 特定商取引法について:インターネット通販等を行う事業者は、事業者の名称・住所・電話番号等を表示する義務があります。これらの表示がないサイトは要注意です。
📊 【保存版】退職後の制度・窓口 かんたん早見表
| 制度(公式名) | ざっくり特徴 | 主な対象例 | 申請・相談先 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険・基本手当 | 失業中の生活支援 | 離職し、求職申込み済の人 |
ハローワーク 要件は公式参照 |
| 再就職手当 | 早期就職に給付 | 基本手当受給資格者で所定要件 |
ハローワーク 支給要件PDF |
| 教育訓練給付 | 受講費を国が一部補助 | 対象講座でスキル養成 |
厚労省/ハローワーク 詳細 |
| 求職者支援制度 | 月10万円+無料訓練 | 雇用保険を受給できない求職者等 |
厚労省/ハローワーク 詳細 |
| 傷病手当金 (健康保険) |
病気・ケガで働けない期間の所得補填。退職後継続の要件あり | 退職前から要件充足等 |
健康保険(協会けんぽ等) 詳細 |
| 受給期間延長 (雇用保険) |
妊娠・出産等で就労不可期間を延長 | 妊娠・出産・育児等 |
ハローワーク 留意点あり |
| 未払賃金立替払制度 | 倒産等で未払い賃金の一部を国が立替 | 倒産企業の離職者 |
労基署・労働者健康安全機構 詳細 |
| 国民年金の免除・猶予 (失業特例) |
前年所得に関わらず免除可(要離職票) | 失業者 |
日本年金機構 詳細 |
| 住民税の減免 | 失業や収入激減で減免の可能性 | 自治体要件を満たす人 |
各自治体 例: 港区・ 練馬区等 |

「"最大数百万円の給付金"って聞くと魅力的だけど…実は自分で無料申請できる公的制度のことピヨ!」
高額なサポート料を払う前に、まずハローワークや健康保険の窓口で無料相談するピヨ〜!
自分で申請すれば、サポート料の15〜30万円を節約できるピヨ🐥💙
📌 まとめ:給付金サポートを使う前に確認すべき5つのポイント
✅ 1. 給付金サポートが案内する制度は既存の公的制度
「最大数百万円」という給付金の正体は、傷病手当金・失業給付・教育訓練給付などの公的制度です。
これらはすべて自分で無料申請できます。
✅ 2. サポート料の相場は給付金の15〜30%(数十万円)
給付金100万円に対して、サポート料は15〜30万円が相場です。
しかし、この手続きは自分で無料でできるものがほとんどです。
✅ 3. まず公的窓口で無料相談が鉄則
ハローワーク・協会けんぽ・自治体の窓口では、無料で丁寧に案内してもらえます。
高額なサポート料を払う前に、まず公的窓口へ相談しましょう。
✅ 4. 運営者情報・料金体系を必ず確認
サイトに会社名・代表者名・住所・電話番号が明記されているか確認。
料金体系や返金条件が曖昧な場合は要注意です(特定商取引法の表示義務)。
✅ 5. 「必ずもらえる」は誇大広告の可能性
給付金の支給には条件があり、「必ずもらえる」「100%受給」などの断定表現は誇大広告の可能性があります。
迷ったら消費者ホットライン(188)に相談してください。
💙 公的制度を正しく理解し、賢く活用しましょう
給付金サポートが案内する制度は、すべて自分で申請できる公的制度です。
まずは公的窓口(ハローワーク・協会けんぽ・自治体等)で無料相談を受け、正確な情報に基づいて判断してください。
数十万円のサポート料を払う前に、自分でできることから始めましょう。