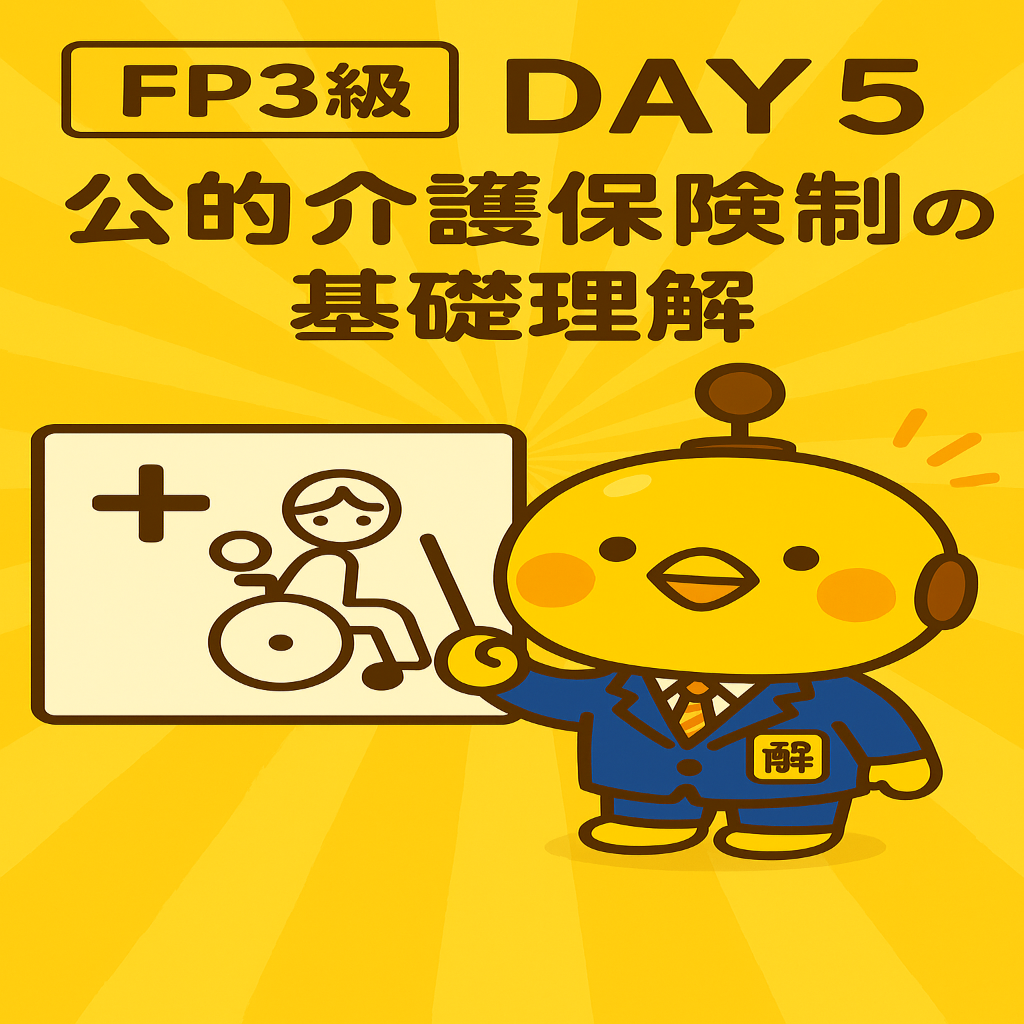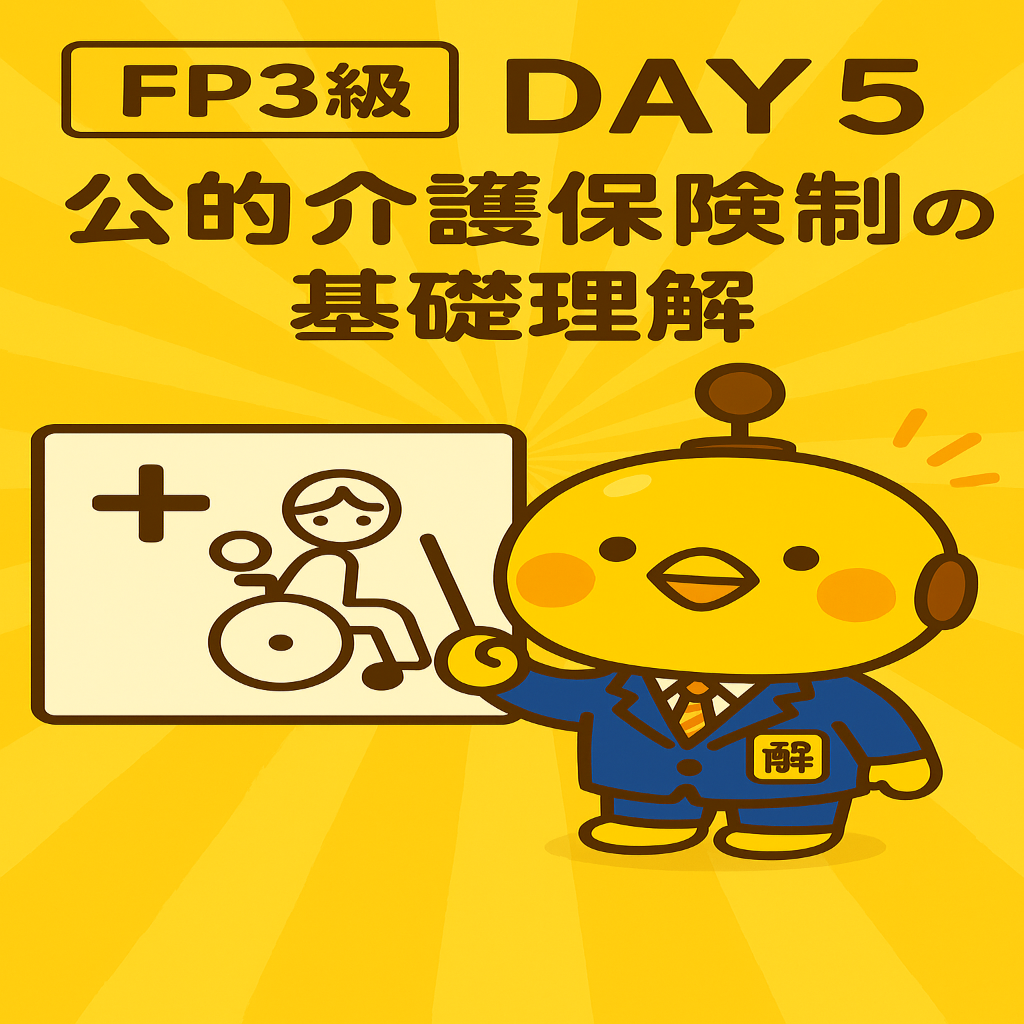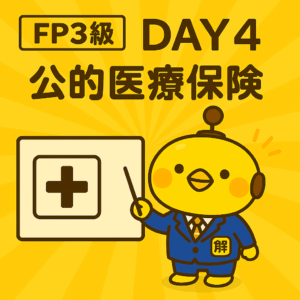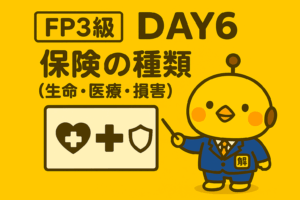【FP3級 DAY5】公的介護保険制度の基礎理解
高齢になったときの介護費用を支える仕組みを理解しよう!
🎧
この記事は音声でも学べます
通勤中やスキマ時間に、音声で介護保険制度について学習できます
※音声と記事の内容は同じです。お好みの方法で学習してください
🎯 今日のテーマ
「高齢になったときの介護費用を支える仕組みを理解する」
→ 介護が必要になったとき、どんな制度でどこまで保障されるのか?を学びましょう!
📗 学習ポイント
🔹 介護保険制度の目的
- 高齢者が要介護状態になった場合でも、自立した生活を継続できるよう支援する制度
- 介護サービスの提供を通じて、家族や地域への負担軽減も図る
- 保険者:市区町村
- 徴収方法:年金から天引き(特別徴収) or 納付書払い
🔹 加入対象と保険者
| 区分 |
対象者 |
内容 |
| 第1号被保険者 |
65歳以上 |
原則すべての人が加入 |
| 第2号被保険者 |
40歳〜64歳 |
医療保険加入者(健康保険・国保など) |
🔹 サービスを受けられる条件
- 要介護認定を受ける必要がある
- 認定は「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7段階
- 市区町村に申請 → 調査員による心身状態調査 → 医師の意見書 → 介護認定審査会で判定
🔹 自己負担割合(所得に応じて決定)
| 所得区分 |
自己負担割合 |
目安(単身世帯) |
| 一般所得層 |
1割負担 |
年収280万円未満 |
| 一定以上の所得者 |
2割負担 |
年収280万円以上340万円未満 |
| 高所得者 |
3割負担 |
年収340万円以上 |
🔹 利用できるサービス例
- 訪問介護、デイサービス、短期入所(ショートステイ)、施設入所など
- 利用できる金額には支給限度額(月額)がある
- ※支給限度額を超過した分は全額自己負担
🔹 図解で理解:介護保険の仕組み
公的介護保険制度(市区町村が運営)
↓
第1号被保険者
(65歳~)
第2号被保険者
(40~64歳)
↓
【要介護認定を受ける】
↓
介護サービス(訪問介護/通所介護/施設入所など)
✏️ Day 5 ミニ確認テスト(○×形式)
各問題について、正しいと思う場合は「○」、間違っていると思う場合は「×」を選択してください
Q1
介護保険の第1号被保険者は65歳以上のすべての人が対象である。
Q2
要介護認定を受けずに介護保険サービスを利用することができる。
Q3
自己負担割合が3割になる可能性があるのは所得が高い人である。
Q4
介護保険の保険者(運営主体)は市区町村である。
Q5
第2号被保険者(40歳〜64歳)は医療保険に加入している人が対象である。
✅ Day 5 テスト結果
正解一覧
Q1: ○ (第1号被保険者は65歳以上のすべての人が対象)
Q2: × (要介護認定を受けないとサービス利用不可)
Q3: ○ (所得が高い人は3割負担になる可能性あり)
Q4: ○ (介護保険の保険者は市区町村)
Q5: ○ (第2号被保険者は医療保険加入者が対象)
✅ Day 5 ミニテスト【解説&深掘り】
✅【Q1】「介護保険の第1号被保険者は65歳以上のすべての人が対象である。」
正解:○
解説:
介護保険の第1号被保険者は、65歳以上のすべての人が対象となります。職業や国籍に関係なく、日本に住所を有する65歳以上の人は自動的に第1号被保険者になります。
第1号被保険者の特徴:
• 65歳になると自動的に加入
• 職業や勤務先に関係なく加入
• 加齢による要介護状態であれば給付対象
• 保険料は年金から天引き(特別徴収)または納付書払い
第2号被保険者との違い:
• 第1号被保険者(65歳以上):すべての要介護状態が対象
• 第2号被保険者(40~64歳):特定疾病による要介護状態のみ対象
❌【Q2】「要介護認定を受けずに介護保険サービスを利用することができる。」
正解:×
解説:
介護保険サービスを利用するためには、必ず要介護認定を受けることが必要です。認定なしではサービスを利用することができません。
要介護認定のプロセス:
1. 市区町村に「要介護認定」を申請
2. 調査員が自宅などに訪問し、「心身の状態」を調査
3. 医師の意見書も加味し、「介護認定審査会」で判定
4. 「要支援1~2」または「要介護1~5」の区分が決定
認定区分:
• 要支援1・2:部分的な支援が必要
• 要介護1~5:介護が必要(数字が大きいほど重度)
• 非該当:サービス利用不可
重要:
この認定を受けないと、制度上のサービスは一切使えません。
✅【Q3】「自己負担割合が3割になる可能性があるのは所得が高い人である。」
正解:○
解説:
介護保険の利用者負担割合は、本人やその世帯の所得状況により決まります。所得が高い人ほど自己負担割合が高くなります。
自己負担割合の詳細(単身世帯の場合):
• 1割負担:年収280万円未満(一般所得層)
• 2割負担:年収280万円以上340万円未満
• 3割負担:年収340万円以上(高所得者)
夫婦世帯の場合:
• 1割負担:世帯収入346万円未満
• 2割負担:世帯収入346万円以上463万円未満
• 3割負担:世帯収入463万円以上
判定方法:
毎年7月末頃に「介護保険負担割合証」で通知されます。年金収入だけでなく、給与・不動産・株などの所得も含めて判定されます。
✅【Q4】「介護保険の保険者(運営主体)は市区町村である。」
正解:○
解説:
介護保険制度の保険者(運営主体)は市区町村です。これは他の社会保険制度とは異なる特徴です。
介護保険の運営体制:
• 保険者:市区町村(運営・管理)
• 被保険者:住民(保険料を払う人)
• サービス提供者:介護事業所・施設
他の制度との比較:
• 健康保険:健康保険組合・協会けんぽが保険者
• 国民健康保険:市区町村が保険者
• 厚生年金:国(日本年金機構)が保険者
• 介護保険:市区町村が保険者 ← 地域密着型
市区町村が保険者である理由:
介護は地域に根ざしたサービスが重要なため、住民に最も身近な行政単位である市区町村が運営しています。
✅【Q5】「第2号被保険者(40歳〜64歳)は医療保険に加入している人が対象である。」
正解:○
解説:
第2号被保険者は40歳〜64歳の人のうち、医療保険に加入している人が対象となります。
第2号被保険者の対象者:
• 会社員(健康保険に加入)
• 公務員(共済組合に加入)
• 自営業者(国民健康保険に加入)
• パート・アルバイト(勤務先の健康保険に加入)
第2号被保険者の特徴:
• 40歳になると自動的に介護保険料の徴収が始まる
• 保険料は医療保険料と一緒に徴収される
• 給付対象は「特定疾病」による要介護状態のみ
特定疾病の例:
がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症など(16疾病群)
🏥 Day5 まとめ
| 問題 |
正誤 |
ポイント |
| Q1 |
✅ |
第1号被保険者は65歳以上のすべての人が対象 |
| Q2 |
❌ |
要介護認定を受けないとサービス利用不可 |
| Q3 |
✅ |
所得が高い人は3割負担(年収340万円超で単身) |
| Q4 |
✅ |
介護保険の保険者は市区町村(地域密着型) |
| Q5 |
✅ |
第2号被保険者は医療保険加入者が対象 |
🔑 介護保険制度の重要ポイント
加入者区分:
• 第1号(65歳以上):全員
• 第2号(40-64歳):医療保険加入者
給付条件:
• 第1号:すべての要介護状態
• 第2号:特定疾病のみ
自己負担:
• 原則1割(所得により2-3割)
• 支給限度額あり
運営:
• 保険者:市区町村
• 地域密着型サービス
🏥 今日のゴール
- ✅ 介護保険制度の目的と仕組みを理解する
- ✅ 第1号・第2号被保険者の違いを把握する
- ✅ 要介護認定の必要性と自己負担割合を覚える
📝 DAY5まとめ
- 介護保険は市区町村が運営する地域密着型の社会保険制度
- 第1号被保険者(65歳以上)は全員加入、第2号被保険者(40-64歳)は医療保険加入者
- 要介護認定を受けることがサービス利用の必須条件
- 自己負担は所得に応じて1割〜3割(原則1割、高所得者は2-3割)
▶ 次回:DAY6「保険の種類(生命・医療・損害)」へ