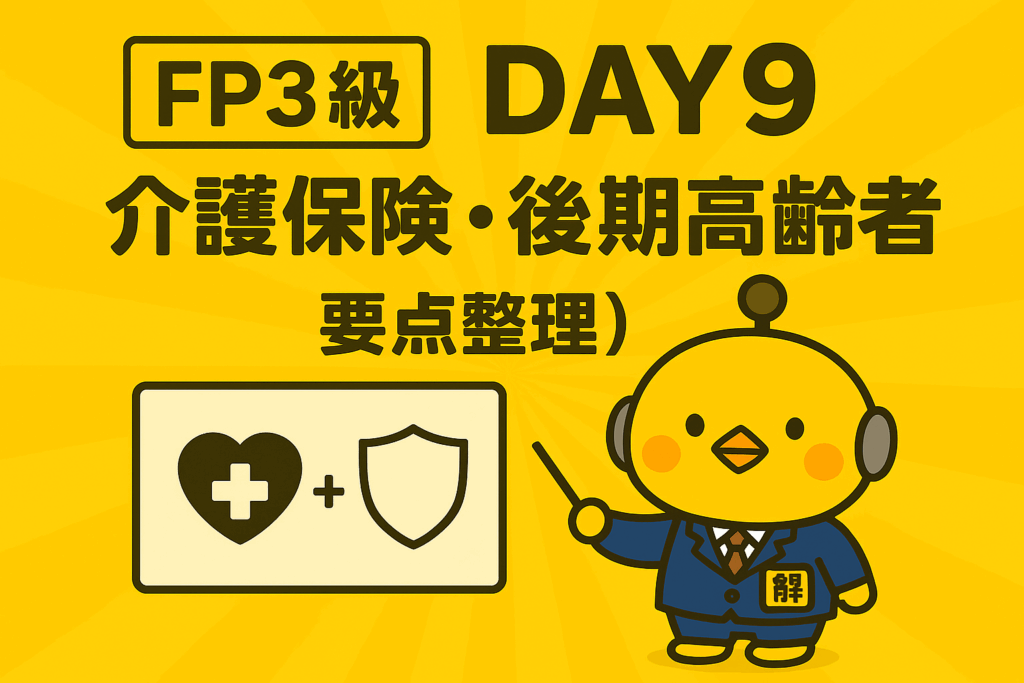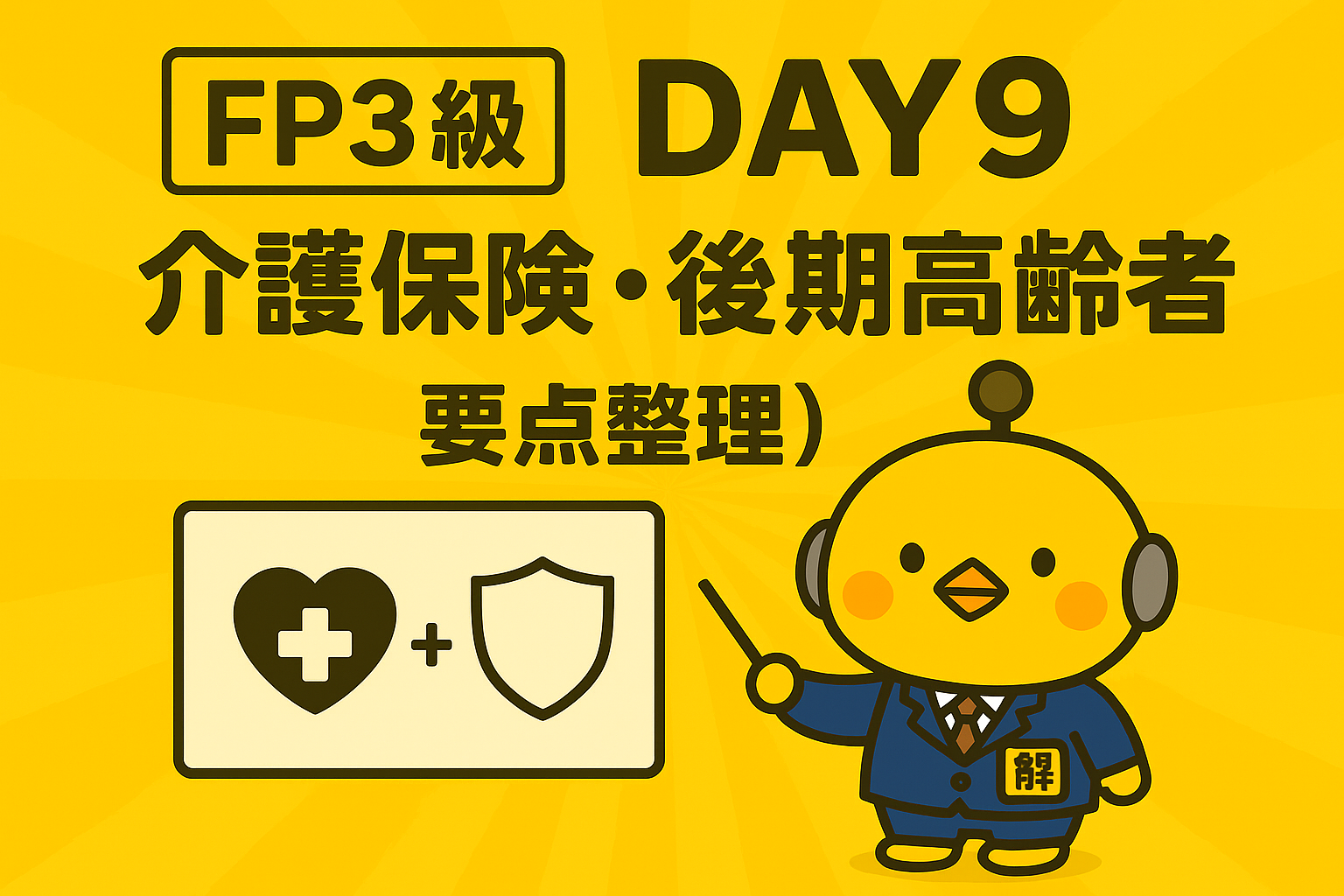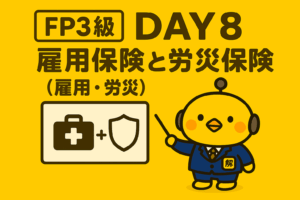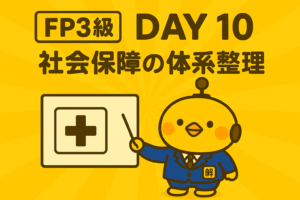【FP3級 DAY9】介護保険・後期高齢者医療の要点整理
高齢期に備える2つの制度「介護保険」と「後期高齢者医療制度」を整理しよう!
🎧
この記事は音声でも学べます
通勤中やスキマ時間に、音声で介護保険と後期高齢者医療制度について学習できます
※音声と記事の内容は同じです。お好みの方法で学習してください
🎯 今日のテーマ
高齢期に備える2つの制度「介護保険」と「後期高齢者医療制度」を整理し、
試験で問われやすい数字と仕組みを正確に理解しましょう。
年齢・保険者・負担割合の細かい条件を覚えることがポイントです。
📗 学習ポイント
🔹 介護保険制度の概要
| 項目 |
内容 |
重要ポイント |
| 創設年 |
2000年施行 |
超高齢社会に対応 |
| 保険料負担 |
40歳から徴収開始 |
20歳からではない |
| サービス利用 |
要介護・要支援認定が必要 |
市町村による認定審査 |
🔹 介護保険の詳細
🏥 介護保険制度
- 創設:2000年施行(超高齢社会に対応)
- 対象者:
- 第1号被保険者:65歳以上
- 第2号被保険者:40〜64歳(医療保険加入者)
- 保険料:40歳から徴収開始
- 負担割合:原則1割(一定所得以上は2割または3割負担)
👥 被保険者の区分
🔸 第1号被保険者
65歳以上の全ての人
🔸 第2号被保険者
40〜64歳で医療保険加入者
🔹 後期高齢者医療制度の詳細
👴 後期高齢者医療制度
- 対象:75歳以上(または65歳以上で一定の障害認定を受けた人)
- 保険者:各都道府県の後期高齢者医療広域連合
- 保険料:年金から天引き(特別徴収)が原則
- 負担割合:原則1割(現役並み所得者は3割)
- ポイント:高齢者医療を一元化して財政を安定させる仕組み
🔍 運営体制
🏛️ 保険者
都道府県の広域連合
🏢 窓口
市区町村
🔹 2つの制度の比較
📊 高齢期の社会保障制度
| 制度 |
対象年齢 |
保険者 |
負担割合 |
| 介護保険 |
40歳〜(保険料)
65歳〜(利用) |
市町村 |
原則1割 |
| 後期高齢者医療 |
75歳以上 |
広域連合 |
原則1割 |
✏️ Day 9 ミニ確認テスト(○×形式)
各問題について、正しいと思う場合は「○」、間違っていると思う場合は「×」を選択してください
Q2
介護保険の第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者である。
Q3
介護サービスを利用するには、要介護または要支援認定が必要である。
Q4
後期高齢者医療制度の対象は原則65歳以上である。
Q5
後期高齢者医療制度の保険者は市区町村である。
✅ Day 9 テスト結果
正解一覧
Q1: × (介護保険料は40歳から徴収される)
Q2: ○ (第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者)
Q3: ○ (介護サービス利用には要介護認定が必要)
Q4: × (後期高齢者医療制度の対象は75歳以上)
Q5: × (保険者は広域連合、窓口は市区町村)
✅ Day 9 ミニテスト【解説&深掘り】
❌【Q1】「介護保険の保険料は20歳から徴収される。」
正解:×
解説:
介護保険は
40歳から保険料を負担します。国民年金は20歳からなので混同注意です。
年齢による制度の違い:
• 20歳〜:国民年金の加入義務
• 40歳〜:介護保険料の負担開始
• 65歳〜:介護保険第1号被保険者
試験ポイント:
「介護=40歳〜」「第1号=65歳以上」で覚えましょう。20歳からの国民年金と混同しやすいので注意が必要です。
保険料の徴収方法:
40〜64歳は医療保険料と合わせて徴収、65歳以上は原則年金から天引きされます。
✅【Q2】「介護保険の第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者である。」
正解:○
解説:
40〜64歳の人は医療保険に入っていれば第2号被保険者になります。介護リスクは40歳から国が備える設計です。
被保険者の区分:
• 第1号被保険者:65歳以上の全ての人
• 第2号被保険者:40〜64歳で医療保険に加入している人
第2号被保険者の特徴:
• 公的医療保険に入っていれば自動的に対象
• 介護保険料は医療保険料と合わせて徴収
• 特定疾病による要介護状態の場合のみサービス利用可能
試験ポイント:
「医療保険加入者」という条件がポイントです。単に40〜64歳というだけでなく、医療保険に入っている必要があります。
✅【Q3】「介護サービスを利用するには、要介護または要支援認定が必要である。」
正解:○
解説:
市町村に申請し、認定審査を受けて「要支援/要介護」の区分が決まります。認定がないとサービスは使えません。
認定区分:
• 要支援1・2:軽度の介護が必要
• 要介護1〜5:介護の必要度に応じて5段階
認定の流れ:
• 市町村への申請
• 調査員による訪問調査
• 医師の意見書
• 介護認定審査会での判定
試験ポイント:
介護保険料を払っていても、認定を受けなければサービスは利用できません。これは介護保険制度の重要な特徴です。
❌【Q4】「後期高齢者医療制度の対象は原則65歳以上である。」
正解:×
解説:
対象は
原則75歳以上です。ただし、65歳以上で障害認定を受ければ加入できます。
対象者の詳細:
• 75歳以上:自動的に対象(原則)
• 65歳以上:一定の障害認定を受けた場合のみ
制度の目的:
• 高齢者医療費の増大に対応
• 医療保険制度の財政安定化
• 高齢者医療の一元化
試験ポイント:
「75歳以上」が原則です。65歳と混同しやすいので、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)と区別して覚えましょう。
他制度との関係:
75歳になると、それまで加入していた健康保険や国民健康保険から自動的に後期高齢者医療制度に移行します。
❌【Q5】「後期高齢者医療制度の保険者は市区町村である。」
正解:×
解説:
保険者は「都道府県の広域連合」です。市区町村は窓口業務を担うだけです。
運営体制の詳細:
• 保険者:都道府県単位の後期高齢者医療広域連合
• 窓口:市区町村(住民に身近な手続き)
• 財源:保険料・公費・現役世代の支援金
広域連合にする理由:
• 財政基盤の安定化
• 効率的な運営
• 都道府県レベルでのリスク分散
他制度との比較:
• 介護保険:保険者は市町村
• 後期高齢者医療:保険者は広域連合
• 国民健康保険:保険者は市町村(都道府県も関与)
試験ポイント:
「保険者=広域連合、窓口=市区町村」で覚えましょう。介護保険は市町村が保険者なので、混同しないよう注意が必要です。
🏥 Day9 まとめ
| 問題 |
正誤 |
ポイント |
| Q1 |
❌ |
介護保険料は40歳から徴収(20歳ではない) |
| Q2 |
✅ |
第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者 |
| Q3 |
✅ |
介護サービス利用には要介護認定が必要 |
| Q4 |
❌ |
後期高齢者医療制度の対象は75歳以上 |
| Q5 |
❌ |
保険者は広域連合(市区町村は窓口のみ) |
🔑 試験での覚え方ポイント
🏥 介護保険
• 保険料負担:40歳から
• 第1号被保険者:65歳以上
• 第2号被保険者:40〜64歳
• 保険者:市町村
👴 後期高齢者医療
• 対象:75歳以上
• 保険者:広域連合
• 窓口:市区町村
• 負担割合:原則1割
介護保険料=40歳から、第1号=65歳以上、後期高齢者医療=75歳以上
🏥 今日のゴール
- ✅ 介護保険の第1号・第2号被保険者の違いを理解する
- ✅ 後期高齢者医療制度の対象年齢と保険者を覚える
- ✅ 各制度の年齢条件と運営体制を正確に把握する
📝 DAY9まとめ
📌 覚え方まとめ
- 介護保険料:40歳から負担
- 第1号:65歳以上、第2号:40〜64歳
- 利用条件:「要介護・要支援認定」必須
- 後期高齢者医療:75歳以上(65歳障害例外あり)
- 保険者:広域連合、窓口:市区町村
▶ 次回:DAY10「社会保障全体の体系を整理 」へ